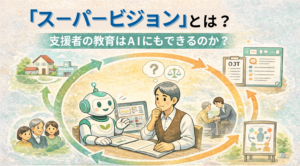生成AIの登場により、障害福祉の現場が大きく変わろうとしています。AI時代、ソーシャルワーカーの役割はどう変わっていくのでしょうか?パパゲーノWork & Recovery(就労継続支援B型)での実践をもとに、AI時代の新しい障害者支援の形を探ります。
この記事は書籍『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』を参考に作成したものです。
誰もがAIを社会資源として使うのが当たり前になる
生成AIを中心としたAIの社会実装が多くの産業に急速な変化をもたらしています。そして、障害福祉・障害者支援はAIの恩恵を最も受ける分野の1つです。
OpenAIのChatGPTを初めて使ったとき、「障害者」という概念や「障害福祉」の常識が根底から変わるのではないかというくらいの衝撃を覚えました。2024年5月13日に発表された「GPT-4o(オムニ:omni)」では、視覚障害のある方がスマートフォンを自分の目の代わりにして街を歩くデモ動画が公開され、心が躍りました。
遠い未来のSF映画のような世界ではなく、誰もが社会資源の1つとしてAIを使いこなし、自分らしい挑戦をしていく社会が数年以内に現実化する話になっています。
 やすまさ
やすまさ視力の悪い方がメガネを使うように、脳の機能障害を「AI」で補い、日常生活をしたり、働いたりするのが当たり前になるのだろうと感じました。
専門知識がなくてもAIが使えるようになった
AIやITツールの活用というと、「数百万円のお金がかかるもの」「ITの専門知識が必要で難しいもの」と身構えてしまう方も少なくないかと思います。
ですが安心してください。今では無料のサービスもあれば、月額数百円から数千円という安価なコストでAIを障害者支援に生かせるようになっています。
しかもITの専門知識や複雑なプログラミングは不要です。音声や文字、画像などで誰でも簡単にAIに指示を出し、使うことができます。つまり、これまでITについてあまり詳しくなかった支援者の方も、障害当事者の方も、今日からAIを使うことができるということです。



例えば、Google Workspaceを契約すると多機能なGeminiが月2,000円以下の金額で使えます。無料版のツールも増えてきています。
「プロデューサー」としての新しい役割
生成AIを誰もが当たり前に使う社会において、ソーシャルワーカー(障害のある方を支援する方)の役割は、従来の「計画作成・紹介役」から、個々のニーズに応じた社会資源を共に開発し、行動に伴走する「プロデューサー」に変わると考えています。
ゼロリスク志向のルールで縛り、画一的な障害福祉サービスを提供する時代は終わります。これからは、個人ごとにAIを活用しながら社会資源を創り出し、行動に伴走していくソーシャルワーカーが求められると予測しています。



新たな社会資源を「作り出す」役割が求められてくると思います。
本当の意味での個別支援がAIによりできるように
就労継続支援B型のような障害福祉サービスを利用する際は、国のルールで個別支援計画という計画書を作ることになっています。ですが、人手や時間が足りず、本当の意味での「個別支援」の実現を諦めている事業所が少なくないのが現状です。
もし、生成AIを使いこなすソーシャルワーカーが「名ばかりの個別支援計画」を本当の意味での「個別支援計画」に変え、障害のある方の希望を形にしていけるとしたら、少しワクワクしませんか?
社会資源として有用なAIを使わずに支援の選択肢を狭めるのは非常にもったいないことだと思います。
ソーシャルワークは時代ごとの最適解を追及する社会科学です。AIが社会を大きく変えたのなら、ソーシャルワークもAI時代に合った形に変化するのが必然です。
実際に新しいテクノロジーを障害福祉に取り入れ、支援現場で生かしている実践知を学ぶことで、現場で生成AIを活用する支援者さんが1人でも増え、「リカバリー」の輪が広がることを願っています。
パパゲーノWork & Recoveryでの実践
僕たちは、2023年9月1日に東京都より「就労継続支援B型(障害福祉サービス)」の指定を取得し、「パパゲーノWork & Recovery(ワーク・アンド・リカバリー)」を日本一大きな精神科病院である都立松沢病院が建つ八幡山駅の近くで開所しました。
障害のある方を対象に、生成AIを活用して上記のような支援を実践してきました。今では100名以上の障害のある方が在籍し、企業のDX支援の仕事を生成AIによる環境調整を活用しながらご活躍いただいてます。うまくいかないこともたくさんありますが、1人1人の挑戦に伴走して、リカバリー(自分らしい生き方の探究)の旅を共に歩んでいます。
AIを活用する障害当事者の事例
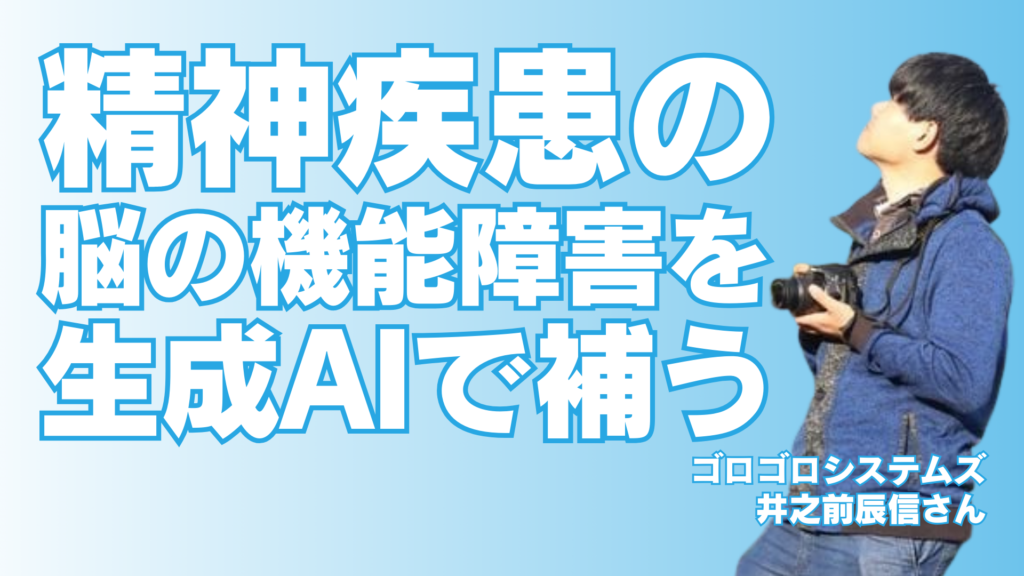
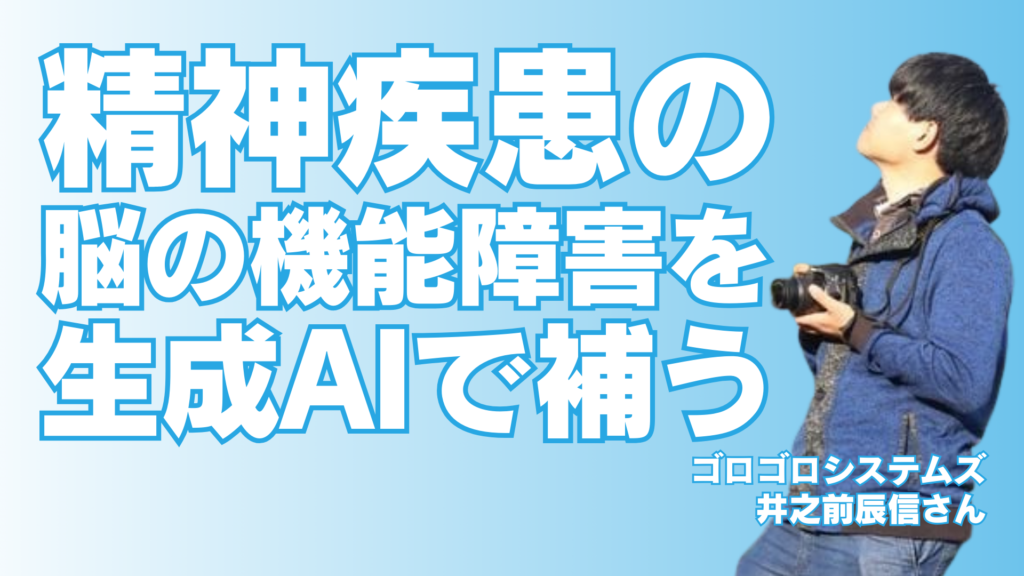






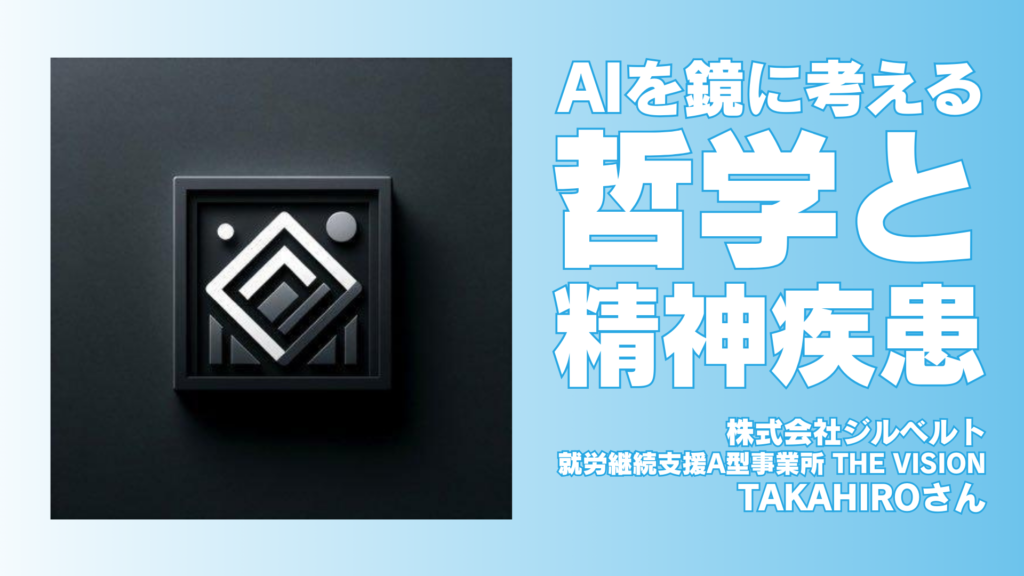
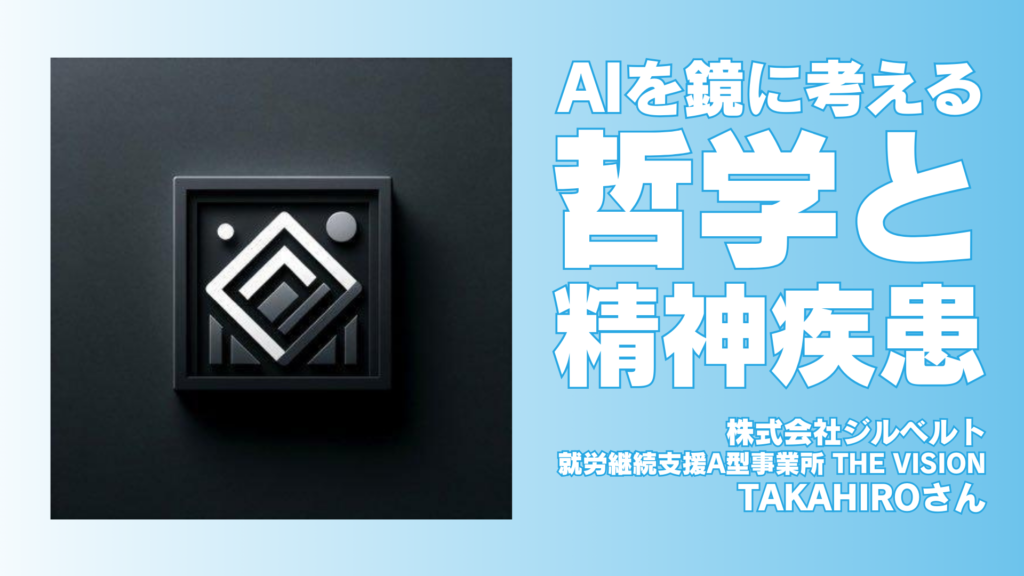



実際に障害のある方が生成AIを活用し可能性を広げている事例は、パパゲーノの公式HPでもご紹介しています!
AIの活用は今日からできる
パパゲーノWork & Recoveryで生成AIを活用し利用者さんのリカバリーを応援している話を共有すると、多くの支援者さんから「パパゲーノさんだからできるんですよ」と返ってきます。
「生成AIを使えば、誰でもできますよ」と言うと、「うちのスタッフはパソコンを使えない人たちだから」「うちは理事がITにうといからAIとかは導入できません」と。
しかし、AIの活用に特別な知識や高額な投資は必要ありません。必要なのは、新しい可能性に挑戦する姿勢と、目の前の利用者さんの希望を本気で実現しようとする熱意です。
AI時代のソーシャルワーカーは、テクノロジーを恐れるのではなく、「社会資源」として活用し、一人ひとりのリカバリーを支援するプロデューサーとして活躍することが求められています。少しでも今日の実践につながることを期待しています。